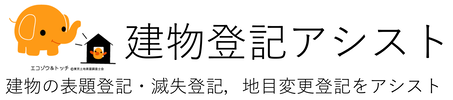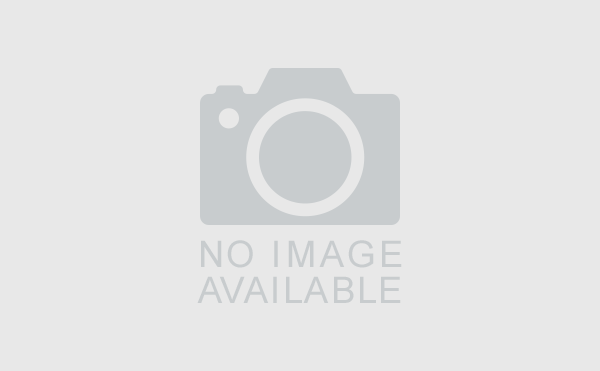戸籍にフリガナが記載されます
令和7年5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナの記載が義務づけられます*1。戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリットとして、行政のデジタル化の推進のための基盤整備、本人確認資料としての利用等があるようです。
土地家屋調査士の業務では所有権確認のために、現在のコンピュータ化された戸籍*2だけでなく、必要に応じ、それ以前の紙で管理された時代の戸籍謄本を調べます。この紙の戸籍には名前に振り仮名を振ることが運用上認められていた時期があるようで、私自身も一部の方の名前に振り仮名が振られているのを見たことがあります。コンピュータ化により振り仮名の運用はなくなったようですが、今回のフリガナの記載の義務化を聞き、思い出した次第です。
*1(以下、法務局HPより)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
*2 現在の戸籍は1994年(平成6年)にコンピュータ化の改正があり、それまで紙ベースで管理されていた戸籍事務がコンピュータ化されることになりました。コンピュータ化の導入時期は市区町村により異なりますが、これまでのB判縦書きから、A4判横書きの書式に変更されました。平成7年から市区町村ごとに導入が始まり、全国すべての市区町村がコンピュータ化されたのは令和の時代になってからのようです。